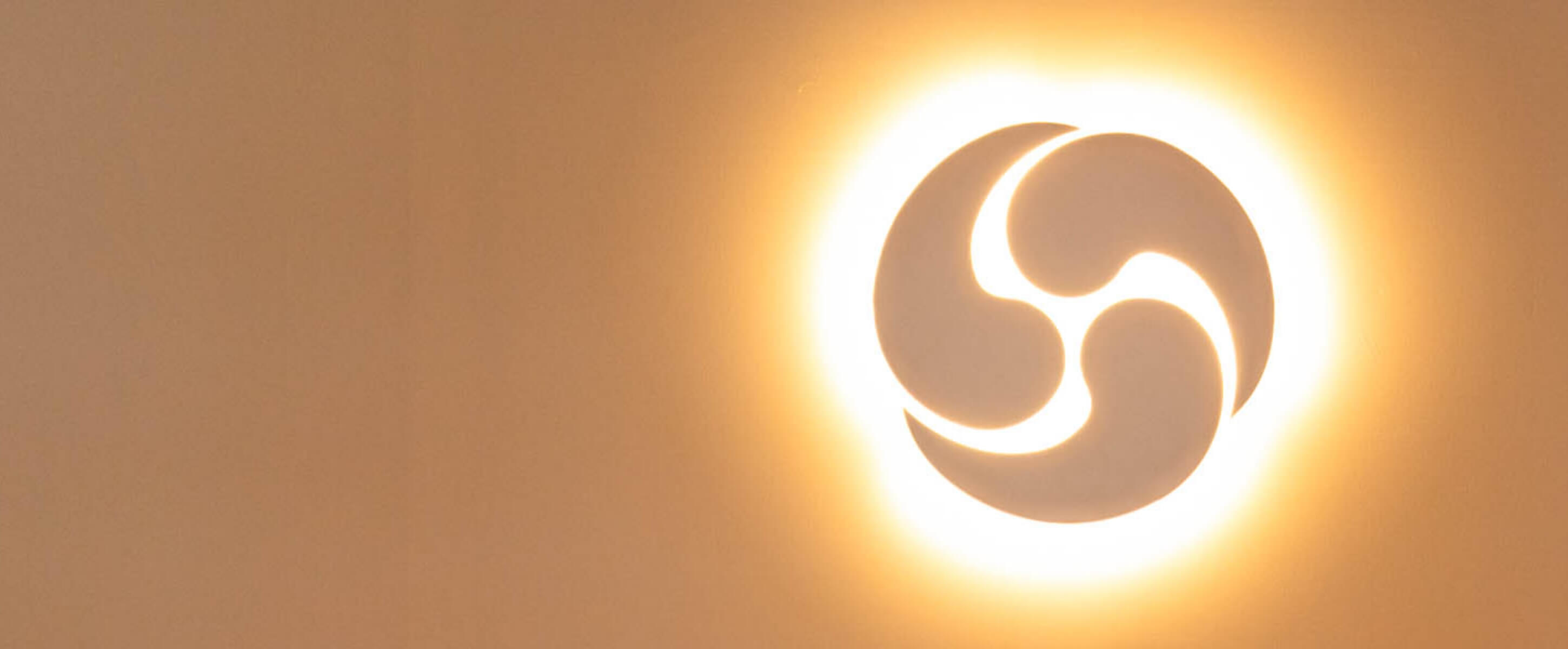歴史 / 教え


概要
建久八年(1197)創建。山号は瑞龍山。
寺紋は越中蜷川氏伝来の右三つ巴。現在は曹洞宗。
本尊の釈迦牟尼仏、県指定文化財の阿弥陀仏、鎌倉開創時本尊の弥勒仏と、
過去現在未来の三世仏が奉安される。
一休禅師ゆかりの火消(汗かき)地蔵尊など仏菩薩が各所に安置される。
蜷川氏元祖の親直、開基親綱、中興開基親煕、
新右衛門で知られる親当などの位牌や墓碑があり、代々が祀られる。
蜷川一族ゆかりの品々が残る。
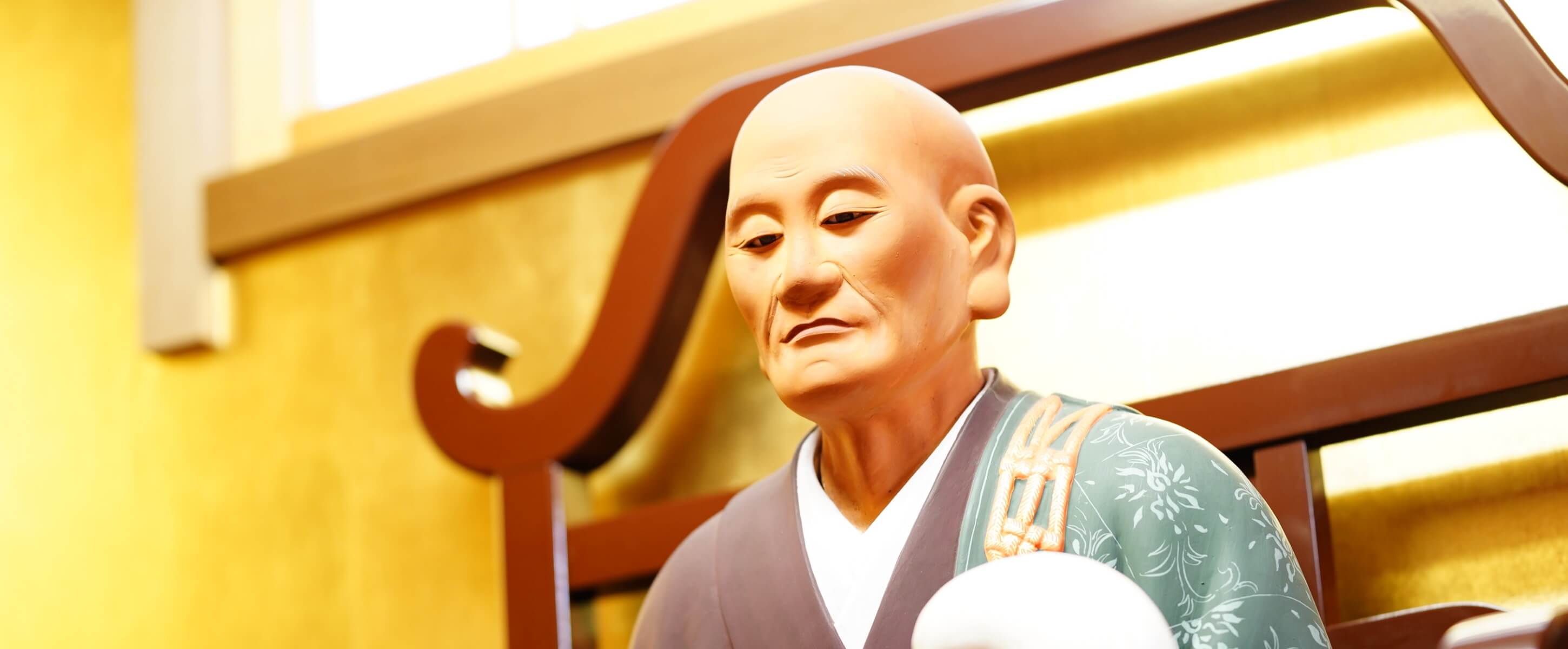
沿革
建久八年(1197)にその蜷川氏元祖である親直を弔うため、嫡子蜷川五郎親綱(ちかつな)が黒崎の地に一寺を建立したのが当寺の始まりである。
以後、蜷川氏代々の菩提所(ぼだいじょ)として、室町時代には一休禅師との親交もあり、臨済宗(りんざいしゅう)であったという。
明応年間(1492~1501)、一族の蜷川八郎親貞(ちかさだ)が出家して独歩慶淳(どっぽけいじゅん)と称し、師僧の亀阜豊寿(きふほうじゅ)を新たに開山に迎え、自らは二世となって曹洞宗(そうとうしゅう)に改宗をする。
永正三年(1506)、守山(もりやま)の神保(じんぼ)氏との戦で越中蜷川氏は敗れ、その際に蜷川城も落城する。当寺も天正十年(1582)に越後上杉氏の戦火で焼失するが、その後、城址に諸堂が復興される。
元禄年間(1688~1704)には、富山藩から寺領も受け隆盛を極めていたが元治元年(1864)に再び本堂・庫裡などを失ってしまう。明治五年に伽藍(がらん)が再興されて修復を重ね今日に至る。
山号は、瑞龍山(ずいりゅうざん)。寺紋は、蜷川氏由来の右三つ巴。本尊の釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)はじめ、県指定文化財の阿弥陀仏(あみだぶつ)、鎌倉開創時本尊である弥勒尊仏(みろくそんぶつ)と、過去現在未来の三世仏(さんぜぶつ)(阿弥陀・釈迦・弥勒)が安置される。一休禅師ゆかりの火消(汗かき)地蔵尊や蜷川氏代々の墓碑などがある。
宗旨
宗 名 | 曹洞宗(そうとうしゅう)(禅宗) |
|---|---|
宗 派 | 曹洞宗は、お釈迦さまより歴代の祖師(そし)方によって相続されてきた正伝(しょうでん)の仏法(ぶっぽう)を依りどころとする宗派です。 |
大本山 | 福井の永平寺 高祖道元禅師(こうそどうげんぜんじ)ご開山 横浜の總持寺 太祖瑩山禅師(たいそけいざんぜんじ)ご開山 |
教 義 | わたしたちはみな仏の子であり生まれながらに仏心を具えています。しかし、それに気づかずに我がまま勝手の生活をして苦しみ悩みのもとをつくっています。 ひとたび仏さまに懺悔し帰依するならば、心がおちついておのずから生活がととのえられて明るくなり社会のお役に立つことを喜び、また、どんな苦難にも耐えて生き抜こうとする信念が生まれます。そこに生きがいと幸福とを発見するのが曹洞宗の教えです。 |
経 典 | 般若心経、観音経、修証義などの諸経典。 |